ご相談・お問い合わせ
-
0467-80-2915
〔受付時間〕9:00~16:00
〔定休日〕日曜日・祝日初回相談「1時間無料」です
お気軽にご連絡ください
コラムCOLUMN
遺言書を作成しておいた方がよいケースとは
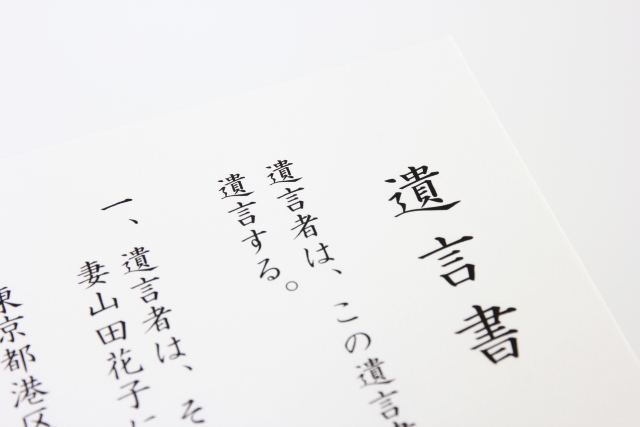
遺言書の作成をためらったり、時間が掛かったりしているうちに、お亡くなりになったり、認知症になってしまい遺言書を作れなくなってしまうこともあります。遺言書の作成は保険と同じです。もしもに備えるものですので、作成に早すぎることはありません。遺言書は元気なうちに作成することをおすすめします。今回は「遺言書が無いことによって、争いが起こりやすいケース」をいくつかご紹介します。
①夫婦に子供がいないケース
夫婦の間に子供がいない場合、残された配偶者と義理の父や母、もしくは義理の兄弟姉妹が相続人になるため、全員で遺産分割協議を行う必要があります。もし、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(甥姪)も遺産分割協議に参加することとなります。そのため、例えば夫が亡くなり、夫名義の自宅や預金を妻名義に変更するには夫の両親または兄弟(または甥姪)の同意が必要になってしまいます。
あまり交流が無い場合や関係が良くない場合は、遺産分割でもめる可能性が高くなってしまいます。
このような状況を回避するために「妻(または夫)にすべての財産を相続させる」旨の遺言書を作っておけば、配偶者だけで相続手続きを進めることができます。
②内縁関係の人、同性パートナーがいるケース
事実上の夫婦ともいえる関係であっても、内縁のパートナーには相続権がありません。
法律上の婚姻関係があれば必ず相続人になれますが、内縁関係のままでは遺産相続に関われないため、財産を遺したいときは遺言書の作成など何らかの対策が必要になるでしょう。
これは同性婚の場合にも当てはまります。同性婚は法律上の婚姻関係ではないため、同性パートナーは相続権を持ちません。そのため、同性パートナーの財産を相続することはできません。
③前妻との間に子供がいるケース
離婚した相手との間に子供がいる場合、こちらに親権がなく、かつ何十年と音信不通の状況であったとしても、その子供は相続人の一人になります。
そのため、再婚の場合、現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含む)離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を行わなければなりません。
相続人同士の関係を考えると、遺産分割協議で揉める可能性は非常に高いと言えるケースでしょう。
④相続人がいないケース
亡くなった人に配偶者や子、父母、兄弟などの相続人がいない場合、相続財産清算人が選任され生前に同居していたなどの特別縁故者がいなければ、その遺産は国に帰属することになります。
遺産を国が取得することを避けるには、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書を作成することにより、お世話になった方や、法定相続人ではない仲の良い親族、慈善団体に遺産を渡すことができます。
⑤意思能力に不安がある人が相続人にいるケース
これは知的障害や精神障害を持つお子様がいらっしゃるご家庭や認知症を患っていらっしゃる方が相続人にいる場合です。相続手続きでは、相続人の意思能力の有無によって異なります。意思能力がないと判断された場合はその人に成年後見人をつけないと話し合いができないのです。成年後見人は一度就任すると基本的に認知症が軽快して本人が意思能力を取り戻すか、本人が死亡するまで成年後見人の職務は終わりません。知的障害のお子様が若い時から成年後見人がついてしまった場合は生涯の成年後見人に支払う費用は多額になります。相続のタイミングで成年後見人をつけなくても大丈夫なように遺言書を作成し、対策しておくことで成年後見人をつけることを回避できます。
当事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。わからないこと、お困り事がありましたら、当事務所までご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせCONTACT
初回相談「1時間無料」です。
お気軽にご連絡ください。
〔受付時間〕9:00~16:00
〔定休日〕日曜日・祝日
全国対応します!
